
自傷行為をする青年とどう向き合えばよいでしょうか。

難しいですね。行動には機能がある訳で、まずその機能を把握しましょう。自傷行為の機能には、情動調整、解離の予防、刺激の探索などがあります。

把握する方法は・・・?

先行刺激、自傷の頻度、型、自傷の結果を聞いてまとめましょう。

先行刺激としては悲しみ、怒りなどネガティブな感情がありますよね。ネガティブな感情は身体疾患により起こり得ますから片頭痛などのcommon diseaseを除外する必要はありそうですね。

はい。もちろん精神疾患が背景にあることも多く、双極性障害のひとが自傷行為を行うことはよく知られています。PTSD、BPDでも自傷行為はありますが、経験上もわかるように、BPDのほうに生じやすいです。

話が少しややこしくなりますが、双極性障害とBPDの合併もよく報告されています。ですからBPDを確定診断したところで留まってしまい双極性障害を疑わないとはならないように注意が必要ですね。

はい。さらに双極性障害とADHDの併存もよくみられ、中枢神経刺激薬で自傷が少なくなったという報告もありますね。
精神療法として情動制御、対人関係効率化、苦悩耐性、マインドフルネスなどの4領域が考えられます。
まず情動制御についてですが、これには身体疾患を安定させる、摂食行動を正常化させること、情動を不安定にする薬物を中止すること、睡眠を正常化すること、運動量をふやすこと、が含まれます。これらの介入でもよくならない場合、さらに対人関係効率化、苦悩耐性、マインドフルネス等へすすみます。
苦悩耐性スキルとしては、「ACCEPT」があります(Activities, Contributing=誰かのために何かをする, Comparisons=もっと悪い状況と比較する, Emotions, Push away, Thoughts, and Sensation)。
参考文献
1 自傷を繰り返す青年に対する精神療法と薬物療法. 臨床精神薬理. 鈴木太. 巻: 25; 号: 2; 開始ページ: 259; 終了ページ: 265.

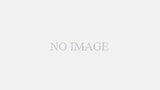
コメント