
SSRIやSNRIなど二種類の抗うつ薬を適切な量、期間使用しても寛解を得ない時、治療抵抗性うつ病といいます。

うつ病によく併存するのが、パニック症、社交不安症、全般不安症です。これらの併存症があるとうつ病は治療抵抗性になりやすくなります。

つまり自殺企図率が上がり、薬物反応率が低下し、多剤併用となるのですね。
うつ病に不安症が併存する率は50%といわれ、両者は密接な関係があります。うつ病と不安症が併存するリスク要因としては、幼少時のトラウマと神経症的傾向があります。
うつ病や不安症の遺伝率はいずれも40%といわれています(遺伝率とは40%の確率で親から子へ遺伝するという意味ではなく、ある疾患が遺伝的な要因によって40%程度決定されることを示します)。また大うつ病性障害(MDD)と不安症は遺伝的脆弱性も共通するという根拠をしめす研究もあります。
画像所見についてですが、まず一般的にいわれていることとしてMDDでは扁桃体(恐怖、不安、記憶の処理)の活性化や容積減少、海馬の容積減少が報告されています。
(余談ですが、脳の一番外側の厚さ4mmのところが灰白色=神経細胞=大脳皮質[このさらに外側が大脳新皮質]で、その下に白質=軸索があります。灰白質は脳の深部にもありますが、そこは大脳皮質とはいいません。脳外科医 澤村豊のホームページ を参照)
MDDでも不安症でも扁桃体の活性化がみられますが、SSRIで扁桃体の活性化は軽減されます。
うつ病に不安症が合併していても、基本はSSRIやSNRIが第一選択で低い用量から開始しアクチベーションシンドロームを避けるためにもゆっくり12週間以上かけて高用量を目指していきます。イミプラミンなど他の抗うつ薬とSSRIで差はないものの、忍容性の面からSSRI/SNRIが第一選択とされています。 第一選択で有効性が確認できなかった場合、非定型抗精神病薬、カバペンチン、プレガバリン(リリカ)を追加することも考えられる。 不安症と診断されなくても、不安性のDSM-5では「不安性の苦痛を伴う」という特定用語があります。「不安性の苦痛を伴う」とは、1)神経過敏、緊張、2)落ち着かない感じ、3)心配のために集中困難、4)何か恐ろしいことが起こるかもしれないという感覚、5)自分自身をコントロールできなくなるかもしれないという感じ、などが特徴とされます。不安性の苦痛を伴うMDDでも治療は基本的には同じであり、SSRIかSNRIを使い、反応が不良であれば、タンドスピロン(セディール、5-HT1A受容体部分作動薬)を追加したり、アリピプラゾール、ブレキシプラゾール(レキサルティ)、クエチアピン、オランザピンなどの非定型抗精神病薬を追加したりします。
参考文献
1 治療抵抗性うつ病に併存する不安症 大坪天平 精神科治療学 Vol.37 No.8 2022年8月号〈特集〉治療抵抗性うつ病への挑戦
2 抑うつと不安 臨床精神医学第51巻第9号(横浜市立大学)浅見 剛・他

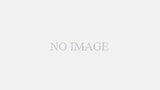
コメント