
まずZドラッグとはなんでしょうか。

ゾルピデム(Zolpidem)、ゾピクロン(Zopiclone)、エスゾピクロンはZを含むことから、この3つの非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬を「Zドラッグ」ということもあります。

そのZドラッグのうち、ゾルピデム(マイスリー 非ベンゾジアゼピン)、ゾピクロン(アモバン 非ベンゾジアゼピン)、それとZドラッグではありませんがトリアゾラム(ハルシオン ベンゾジアゼピン)に夢遊症状に関する注意喚起がされました。

催眠鎮静作用のある抗精神病薬(クエチアピン、レボメプロマジンなど)は睡眠薬の代わりに使用されることもありますがエビデンスがないことに留意しておきたいです。

薬理的な基本として、5-HT1A受容体の遮断は睡眠促進とレム睡眠増加を、5-HT1A受容体の刺激はレム睡眠減少をもたらします。タンドスピロン(セディール)は 5-HT1A受容体作動薬ですからレム睡眠減少(夢がすくなくなる)をもたらします。
睡眠時無呼吸症候群はREM睡眠期に無呼吸イベントがおこりやすいため、抗うつ薬は治療的効果があるという報告がありますが、同疾患の基本的治療はCPAPでありますし、また抗うつ薬による体重増加にも気をつける必要があります。

うつ病で睡眠障害があるとそれは二次性(うつ病が治れば睡眠も良くなる)と考えがちですが、併存すること(うつ病が治っても睡眠障害が残遺する)も多くあり、現在は後者の考え方が主流になってきています。
うつ病と睡眠障害は深い関係があり、うつ病の急性期に60%で不眠があること、不眠が自殺の予測因子になること、軽快後の残遺症状として不眠が最も高いこと、などが知られています。

抗うつ薬の中でも、SSRI、SNRI、賦活系TCAでは、5-HT2受容体の賦活もしくはエピネフリン/ドーパミン神経伝達の上昇により不眠を引き起こす可能性もありますね。

PTSDに関連した悪夢についてはプラゾシン(ミニプレス)が有名ですね。
ここでもう一度睡眠薬を整理してみましょう。
バルビツール酸系、非バルビツール酸系、ベンゾジアゼピン受容体作動薬≒GABA-A受容体作動薬、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬があります。
ベンゾジアゼピン受容体作動薬≒GABA-A受容体作動薬はさらに、ベンゾジアゼピン系と、非ベンゾジアゼピン系≒Z-Drugの二種類に分けられます。
ベンゾジアゼピン受容体作動薬≒GABA-A受容体作動薬の中では、ベンゾジアゼピン系より、非ベンゾジアゼピン系≒Z-Drugの方が身体依存のリスクが低いといわれています。そのため不眠症の治療薬のフェースチョイスは、非ベンゾジアゼピン系≒Z-Drugか、メラトニン受容体作動薬か、オレキシン受容体拮抗薬のいずれかが最適でしょう。
高齢者の場合、ベンゾジアゼピン受容体作動薬≒GABA-A受容体作動薬は認知機能低下のリスクがあります。断薬により可逆的に回復される場合が多いとされますが、稀ですが不可逆に認知症になる場合もあります。
ですから高齢者であれば、メラトニン受容体作動薬か、オレキシン受容体拮抗薬のいずれかが良いかもしれません。
trazodone(デジレル、レスリン)は鎮静系抗うつ薬として不眠にもよく使用されますが米国では推奨をうけていません。不眠をターゲットに使用する場合は、血中濃度の上昇が睡眠薬に比べて遅いため入眠の2時間くらいまえに服用するとよいでしょう。事前にこの知識がない患者様が経験的に入眠の1-2時間前に内服されることにより良眠を得ていたことがあり、非常に驚いたことがありました。
ナルコレプシーの治療には精神刺激薬が使用されるがそれには情動脱力発作(カタプレキシー)の抑制作用はない。情動脱力発作の治療は、クロミプラミン(アナフラニール。保険適応あり)やベンラファキシン(イフェクサー。保険適応なし)が使用されます。しかも抗うつ効果よりもカタプレキシー抑制効果の方が即効的です。さらに興味深いのは抗うつ薬のカタプレキシー抑制効果が耐性を生じることがある点です。
REM睡眠行動障害(RBC)とうつ病はよく併発します。これはどういう関係なのでしょうか。まず特発性RBDの発症年齢は60歳以降であり、ドーパミン系と関連したα-synucleinopathy(α-シヌクレオイドパチー)という病態が考えられています。α-synucleinopathyは、神経変性疾患の一種で、α-シヌクレオイン(α-synuclein)というタンパク質の異常蓄積が原因で起こる疾患群の総称で、パーキンソン病、多系統萎縮症、レビー小体型認知症などが含まれます。つまり特発性RBCは高齢者の病気というイメージです。一方、うつ病治療を長くうけている方に二次性RBCがみられた場合その発症は40~50歳です。これは、α-synucleinopathyが低年齢で発症したのでしょうか、それとも抗うつ薬による「筋放電の抑制を欠くREM睡眠増加」によりRBCが文字通り二次性におきたのでしょうか。セルトラリンで「筋放電の抑制を欠くREM睡眠増加」は増加しますが、RBCの症状を発現される基準にまでは達さなかったという報告もあり、まだ結論はでていません。
restless legs症候群(RLS)とうつの関係を、A)RLS罹患中にうつ状態になった場合と、B)うつ状態になった後に二次的にRLSを呈している場合とに分けて考えてみます。A)の場合はRLSによる断眠がうつ症状の原因になっている可能性があり、抗うつ薬の効果は期待できないため、ドパミン受容体作動薬などによりRLSの治療をします。B)の場合は、ミルタザピンやベンラファキシンがRLSの原因となりやすいため、SSRIやtrazodoneを使うとよいでしょう。
睡眠薬のいわゆる「出口戦略」ですが、できれば最初から睡眠薬を処方せず、それと同じ有効性でかつ長期効果や安全性では睡眠薬よりも優れていて欧米では第一選択である認知行動療法で不眠を治せれば理想的です。しかし本邦では保険適応になっておらず日常診療においては現実的ではありません。認知行動療法の短所として効果発現に数か月を要する点があります。
睡眠薬を減らす方法に漸減法や隔日法があります。どちらも2-4週間毎に、25%ずつ減らす方法です。例えば2錠飲んでいる場合、まず1錠と半錠(1.5錠)にして一ヶ月間すごし、そのまた次の一ヶ月は1錠にしてみて、さらに次の一ヶ月は半錠にしてみるということです。
夜勤シフトの人は概日リズム(太陽のサイクルと体内時計のリズムが合わない)が不安定になってしまいますが、夜勤シフトをやめてから2-3年はそれが残ってしまうともいわれているので注意が必要ですね。
参考文献
1 精神疾患における睡眠問題とその治療に関する諸課題 三島和夫 著 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 10, 1059 – 1069 (2022)
2 抗うつ薬と睡眠 著者: 井上雄一 出典: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 10, 1087 – 1095 (2022) 出版社: 星和書店
3 不眠症における睡眠薬治療 著者: 高江洲義和 出典: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 11, 1205 – 1212 (2022)
4 不眠医療のガイドラインの有用性と限界 著者: 三島和夫 出典: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 6, 677 – 684 (2022)
*ご利用上の注意について
本サイトは、患者様、医療関係者の皆様などに日常生活や仕事が少しでも快適になることを目的としております。 また、本サイトに掲載されている情報は管理、点検しておりますが、必ずしも常にその確実性が保証されるものではなく、情報のご利用については、ご利用される皆様の判断にまかせられることを前提としています。 本サイト運営においては適時情報の更新等行って参りますが、万一本サイト情報の利用の結果、不都合や不利益が発生することがありましても、情報の提供者側は最終的な責任を負いかねますことをご理解いただき、慎重にご利用くださいますようお願い申し上げます。
本サイトにリンクを希望される場合は、あらかじめ下記の注意事項すべてに従ってください。 また、本サイトへのリンクにより、万一、貴社または貴殿が損害を被った場合、および第三者との間に何らかの紛議が生じた場合でも、損害賠償等の義務・責任を負いませんので予めご了承願います。 本サイトへのリンクは、ホームページを利用されるユーザーの皆様の便宜を図ることを目的とする場合に限ります。それ以外本サイトの目的に該当しない下記の場合におけるリンクは固くお断りいたします。
1. 本サイトにリンクすることにより、本サイトと特別な関係があるように見せかけたり、リンクの設定自体を営利目的とするもの。
2. 本サイトの社会的信用を損なうおそれがあるもの。
3. 違法のおそれ、または公序良俗に違反するおそれのあるサイトからのリンク。
4. フレーム・インラインフレーム等の技法により本サイトのコンテンツであることが不明確となるもの。
本サイト上のコンテンツ(情報、資料、画像等)の著作権については、本サイトが保有または管理しております。本サイトの許可なくコピー、販売・転売、転用など2次的に利用することは固く禁じます。 本サイトの許可なく上記著作権に関する一切の再利用は法律で禁じられています。

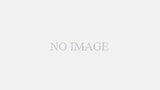
コメント