
1960年代までは「超自我が未熟な児童においてはうつ病は起こり得ない」と考えられていましたが、海外のメタアナリシスではうつ病の発症ピークは15-16歳という報告があります。
思春期のうつ病の有病率*は11%というデータもあります。

児童思春期においては表現形式に特徴があります。成人にみられる悲哀は苛立ちや恐怖、興味喪失はスマホをぼーっと長時間見続ける、などに置き換わります。本来とはまるで逆の症状、易怒、反抗挑発などがみられることもあります。

*有病率は、ある一時点において、疾病を有している人の割合です。時間をとめて、その時に何人が病気をもっているかということですね。
一時期、パキシルによる自殺行動が社会的にも問題となりましたが、このリスクはSSRI間で大きな違いはないことがわかってきました。抗うつ薬と自殺行動の関連理由ははっきりとわかっていませんが、中枢神経系の脆弱性や双極性要素の存在などが想定されています。投与最初の9日間は特に注意が必要でしょう。
思春期のうつ病に対して三環系四環系抗うつ薬はドロップアウトが多かったり、逆に抑うつ症状を増悪させるため、ふつうは用いません。またベンラファキシン(商品名:イフェクサー)は自殺念慮を増悪させる可能性があり用いにくいです。
思春期の双極性障害の治療についても考えてみましょう。
思春期の躁病エピソードの場合、成人と同じように炭酸リチウムの効果があります。思春期の双極性障害にはADHDを合併することもよくありますが、その場合は炭酸リチウムよりもリスペリドンが有効であるという報告もあります。ADHDと双極性障害の併存がある場合、基本的に双極性障害を先に治療します。ADHD治療薬は気分が安定していないと、双極性障害の症状を増悪させる可能性があるからです。
思春期の抑うつエピソードの場合、ルラシドン(商品名ラツーダ)の優位性が報告されています。
参考文献
1 子どものうつ病は見逃されているのか (東海大学)木本 啓太郎・他 臨床精神医学第52巻第1号
2 思春期の抑うつ障害,双極性障害の薬物療法 辻井 農亜 臨床精神薬理 第25巻03号 2022年03月

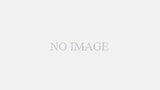
コメント