
もともとバルプロ酸はてんかん薬でしたが、躁状態にも有効です。

メタ解析では躁状態に対してバルプロ酸はリチウムより有効性は低いのですが、忍容性(副作用に耐えられる程度)は高いとされます。

バルプロ酸で躁状態を治療するとき、血中濃度は75~99がよいようです。

一方で抑うつエピソードに対するバルプロ酸の効果は議論がわかれますね。

お薬の使い方はとても難しいので、お困りの方はネットの情報に頼らずに必ず病院に行きましょう。
バルプロ酸の抑うつエピソードに対する有効性は研究によって異なり、無効という報告もあります。
気分エピソードに対する維持療法、つまり再発防止についてはどうでしょうか。これも研究により意見が分かれていて血中濃度75~99μg/mlが維持されていれば気分エピソードの再発予防効果があったとする報告と、維持療法にバルプロ酸は有用ではないとする報告があります。
双極性障害の維持療法としては標準的な治療濃度は0.6~0.8mEq/Lであり、効果と忍容性(副作用の程度)をみながら増減するとよいかもしれません。ただし65歳以上の高齢者については腎機能障害などの副作用がでやすいので0.4~0.6mEq/Lくらいの低めを目指すとよいかもしれません。
以上より躁うつ病ではやはりリチウムが第一選択で、それで副作用があればバルプロ酸に切り替えますが、躁うつ病のうつについての効果はあまり期待できないということになります。 内服を継続することにより吸収、代謝、排泄がある定常状態へ達します。一般的に半減期の5-6倍を経過すると定常状態に達します。バルプロ酸の場合半減期が6-20時間で3-5日程度で定常状態に達することになります。
バルプロ酸は催奇形性リスクが高いことにも注意しなければいけません。
参考文献
1 血中濃度からみた気分安定薬の処方時の注意点 肥田裕丈: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 1, 33 – 41 (2022)

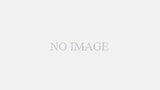
コメント