
躁うつ病といえばリチウム、リチウムといえば躁うつ病と考える医師が多いのではないでしょうか。

そのイメージはエビデンスからも正しいといえるかもしれません。躁病エピソードに対するリチウムの至適濃度は高めの0.8~1.0が推奨されています。抑うつエピソードについての至適濃度は特に推奨されていませんが、躁病エピソードの場合と比べて低くても良いという訳ではなくケースバイケースに考えましょう。

躁うつ病の維持期の血中濃度はどうすればよいでしょう。

維持期の至適濃度は研究によって違いがありますが0.6~0.8を基準として、効果をみながら増減するとよいでしょう。ただし65歳以上の高齢者については、腎機能障害などの副作用がでやすいので0.4~0.6くらいの低めを目指しましょう。

血中濃度はいつ測定すればよいでしょうか。

5日間くらい内服を続けると定常状態になります。そして血中濃度は濃度が最低になるトラフ値を採用すべきなのですが、一般的に最終服薬後12時間後が推奨されています。

薬物相互作用についてはいかがでしょうか。

SSRI、SNRI、ミルタザピンとの併用はセロトニン症候群のリスクがあります。カフェインによりリチウムの濃度が下がりますので、急にカフェインをやめるとリチウム濃度が急に上がって思わぬ副作用が出現してしまうことがあります。

とても怖いのがリチウム中毒ですね。

腎機能低下時、降圧剤や利尿剤服用、脱水、NSAIDSなどはリチウム中毒を引き起こすことがあるので注意しましょう。

お薬の使い方はとても難しいので、お困りの方はネットの情報に頼らずに必ず病院に行きましょう。
躁病エピソードに対してリチウムは様々な国際治療基準においてファーストラインとされており、至適濃度は高めの0.8~1.0mEq/Lが推奨されています。
抑うつエピソードについては各ガイドラインにおいて明確な至適濃度の推奨はありません。抑うつエピソードにおいては血中濃度は低くてもよいということではありません。
双極性障害の維持療法としては標準的な治療濃度は0.6~0.8mEq/Lであり、効果と忍容性(副作用の程度)をみながら増減するとよいかもしれません。ただし65歳以上の高齢者については腎機能障害などの副作用がでやすいので0.4~0.6mEq/Lくらいの低めを目指すとよいかもしれません。
内服を継続することにより吸収、代謝、排泄がある定常状態へ達します。一般的に半減期の5-6倍を経過すると定常状態に達します。リチウムの場合半減期が18時間で5日程度で定常状態に達することになります。血中濃度の測定は濃度が最低になるトラフ値を採用すべきなのですが、リチウムの場合は最終服薬後12時間後の測定が推奨されています。
リチウムと他の物質の相互作用ですが、カフェインはリチウムの血中濃度を下げるので双極性障害の患者様がリチウムとカフェインを併用することは症状変動に関係することがあり注意を要します。NSAIDs、利尿剤、ACE阻害薬、カルバマゼピンはリチウムの血中濃度を上げます。リチウムは、三環系との併用よりも、SSRI、SNRI、ミルタザピンとの併用においてセロトニン症候群(不安、混乱、いらいら興奮、動き回る、体がぴくぴく動く、震える、汗をかく、熱がでる、下痢になる、脈が速くなるなど)のリスクが高まるとされます。
*ちなみに三環系は、電気けいれん療法と相性がよろしくありません。
またリチウム中毒や催奇形性などの副作用にも十分注意しなければいけません。
1.5mEq/L を超えるとリチウム中毒を起こす可能性があるといわれます。ただし血中濃度が治療域でも重篤な臨床症状を呈することがあり注意が必要です。 5重症度別に軽度または中等度(1.5-2.5mEq/L)、重度(2.5-3.5mEq/L)、生命に危険を及ぼす中毒( >3.5mEq/l)と分類されます。
参考文献
1 血中濃度からみた気分安定薬の処方時の注意点 肥田裕丈: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 1, 33 – 41 (2022)
2 厚生労働省 リチウム中毒 重篤副作用疾患別対応マニュアル

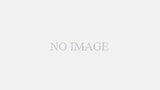
コメント