ブロナンセリン(ロナセン)はDSAといい、SDAよりドパミン受容体への親和性が高いです。SDAやMARTAと比べてメタボリックな副作用は少ないです。また1日1回貼付のテープ剤があるのも特徴です。
抗精神病薬ではブロナンセリン(ロナセン)だけが子どもの統合失調症に対して保険適用になっていますね。
子どもはメタボリックな副作用に弱いのでその点も考慮されてのことかもしれません。
お薬の使い方はとても難しいので、お困りの方はネットの情報に頼らずに必ず病院に行きましょうね。
セロトニン受容体拮抗薬とドパミン受容体拮抗薬を併用すると錐体外路症状がなくなったことからセロトニン・ドパミンアゴニスト(SDA)やドパミン・セロトニンアゴニスト(DSA)が開発されました。DSAは、SDAと比較してドパミンへの親和性がより高く、ブロナンセリン(ロナセン)がこれに相当します。
脳内には4つのドパミン作動経路があり、中脳辺縁系、中脳皮質系、黒質線条体系、漏斗下垂体系といわれます。統合失調症の陽性症状は中脳辺縁系のドパミン機能が亢進すると生じ、陰性症状は中脳皮質系のドパミン機能が低下すると生じます。セロトニン受容体拮抗作用をもつ抗精神病薬は、中脳皮質系のドパミン機能を抑えるとともに、セロトニン受容体拮抗作用により中脳皮質系のドパミン機能を高めることにより陰性症状にも効果をあらわします。
急性期には抗精神病薬の量は増えがちですが、維持量の見極めや遅発性ジスキネジアや過感受性精神病等の問題があるため、抗コリン薬を使用せずにEPSを生じさせない量が理想的です。
ブロナンセリンはドパミンD2受容体やD3受容体への親和性がセロトニン5-HT2Aよりも強く、また他の受容体への親和性は低く、シンプルな結合特性をもっています。
ブロナンセリンのもつD3受容体遮断作用は過感受性精神病の発症予防や認知機能や社会性の改善に効果があるかもしれないといわれています。
参考文献
1 Blonanserin の薬理学的特性と最近の非臨床研究 野田幸裕, 肥田裕丈 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 2, 195 – 203 (2022)




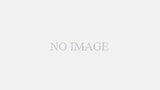
コメント