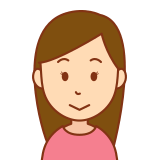
パキシル40㎎を8週間内服しても抑うつ気分、興味喜びの消失が改善しませんでした。それでパキシルをやめてイフェクサー225㎎を4週間内服していますが、やはり改善がありません。

お辛いですね。SSRI/SNRIの二種類で効果がありませんでしたから治療抵抗性うつ病かもしれません。

リチウム(例 600mg/日。至適濃度0.5-1.1、中央値は0.6mEq/L)、ミルタザピン、オランザピン、クエチアピン、アリピプラゾール(3mg)、レキサルティ(1-2mg)などを併用すると改善するかもしれません。

他にもECT、そしてECTより効果は劣るものの麻酔の必要がないrTMS(2019年より保険適応)がありますね。
治療抵抗性うつ病と関連する特徴をあげてみます。一つ目が精神病性の特徴を伴う場合です。古典的なメランコリー(≒生物学的うつ病)のうちの一類型である退行期メランコリーが現代でいう精神病性うつ病とほぼ一致します。治療は抗精神病薬の併用やECTです。2つ目が緊張病を伴うがカタレプシー(受動的にとらされた姿勢を保ち続け、自分の意思で変えようとしない状態。蝋屈症)はない、つまりうつ病性昏迷です。統合失調症の緊張病よりもベンゾジアゼピン大量療法で改善しやすいといわれています。3つ目が虐待を含む外傷体験です。HPA-axis研究においてもうつ病とは違いPTSDでみられる抑制型のパターンを示します。4つ目が一時期メディアで騒がれた、自分の趣味などは楽しめる、つまり気分の反応性が保持されている「新型」「現代型」「逃避型」などといわれるうつ病で、これに対する過度の医療化には議論が続いています。
以下は主観でありエビデンスは全くありませんのでその点をご注意してお読みください。リチウムと抗うつ薬の併用はすごく効果があります。これは臨床医にとっては常識であり、増強療法として広く認知されていますが、リチウムはセロトニン症候群やリチウム中毒などの副作用があったり、濃度測定が必要であったりして、抗うつ薬との併用を先延ばししてしまうことがあるのではないでしょうか。さらにこの「増強」という言葉が少し誤解を招く気もいたします。あくまで個人的な印象ですが、抗うつ薬を増量しても併用しても全く効果がでず、「ひょっとして性格の特徴ではないか」と思うくらいに抗うつ薬への反応、言い換えると治療者側の薬物治療の手応えが全くないケースでリチウムの増強療法が著効するきがいたします。つまり「抗うつ薬で半分位改善したからリチウムでもうひと押し、『増強』」というのではなくて、「これだけ抗うつ薬を使っても症状がひとつも変わらないから、性格や神経症の範疇ではないか」という場合にあっさり効いて「しまう」印象があるのです。無論、治療側が難治例となるまでリチウムを処方していないだけというバイアスもあろうかとは思います。上記のようなリチウムが奏功する方は明らかな運動抑制があるようにもみえず、会話もしっかりできていらっしゃって思考抑制もなさそうであり、では不安焦燥や抑うつ気分が強いかというと非常に落ち着いた態度で(これが症状を軽症にみせてしまうのかもしれません)、「なんだかだめなのですよねぇ」「ちょっと調子わるかったかな」という表現であります。もともとローテンションの人なのかなと思わせるのですが、でも表情はやはり生気がなく、問診をすすめると自傷行為や自殺念慮が慢性・断続的にみられていらっしゃるという印象があります。
さて、治療抵抗性うつ病の話題からすこしだけ話がずれます。一種類目の抗うつ薬の効果がなかった場合にどうするかという「そもそも論」です。
国際、国内のガイドラインでは周知のとおり、「現在処方している薬を増量する」のがよいとされています。しかし用量ー反応関係のエビデンスがあるのは実は三環系四環系とSNRIだけであり、他の薬は増量した場合の副作用のデメリットの方が大きいという意見もあります。
エスシタロプラム10mg、パロキセチン20mg、セルトラリン50mgが最適でそれ以上増やしても意味はなく、次の一手を考えるべきだということです。
維持治療については、抗うつ薬の用量をできるだけへらし、初回エピソードなら4-9か月、再発なら2年以上継続するのがよいとされています。
参考文献
1 治療抵抗性うつ病の薬物療法 南翔太,加藤正樹 精神科治療学 Vol.37 No.8 2022年8月号〈特集〉治療抵抗性うつ病への挑戦
2 治療抵抗性うつ病の見立てと治療─今後の展望─ (京都大学)諏訪 太朗 臨床精神医学第52巻第1号
3 うつ病治療における抗うつ薬の用量 著者: 田近亜蘭, 古川壽亮 出典: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 12, 1311 – 1317 (2022)

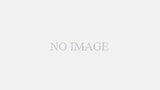
コメント