
緊張病(カタトニア)の症状は、無言症、筋強剛、一点凝視、常同運動、昏迷があります。

カタトニアの症状のひとつとして昏迷があるわけですね。

精神科でいう昏迷とは意識障害はなく外界を認識しているが、これに応じる意志が発動されないことをあらわします。無言無動で痛み刺激に反応しないこともあります。

悪性症候群を緊張病(カタトニア)の一タイプ(悪性カタトニア)として考える人もいます。
緊張病とカタトニアという専門用語の違いですが歴史的な治療の変遷が関わっています。緊張病といわれていた時代はハロペリドールの注射などがされていました(現代の医学ではむしろ症状増悪させるものとして否定されています)。しかしFlinkとTaylarによる「カタトニア」という本が出版されてから、治療が大きく変化・前進しました。
まずカタトニアには、精神疾患によるものと、身体疾患によるものがあることを理解しましょう。脳脊髄炎や代謝障害でもカタトニアは起こり得るため、カタトニアをみたらすぐに「ベンゾジアゼピン系の薬だ、mECTだ」という治療に先走らずに、身体疾患の除外が大事です。
カタトニアの代表的な診断基準のひとつをあげます。
表 Fink と Taylor が推奨するカタトニアの診断基準
A .無動,無言,昏迷が少なくとも 1 時間持続し,以下の症状を少なくとも 1 つ以上伴う:
カタレプシー,命令自動,姿勢常同
B .無動,無言,昏迷がない場合,以下の症状が少なくとも 2 つ以上,2 回以上観察または誘発される:
カタレプシー,命令自動(指示への自動的な服従),姿勢常同,常同症(反復的で異常な頻度の,目標思考のない運動),反響現象(他人の行動をまねる。反響言語や反響動作),拒絶症,両価性
カタレプシーと蠟屈症の相違がわかりづらいのですが、カタレプシーは、受動的に取らされた姿勢を重力に抗したまま保持することで、蠟屈症は検査者に姿勢をとらされることを無視し抵抗さえする状態です。
また両価性も例をあげないと理解が難しいです。これは被影響性の亢進ととらえられます。医師が患者様に握手をするかのように手をさしのべながら「握手をしないでください」というと、患者様は手をだしたりひっこめたり、もしくは軽くだけ医師の手を触れたりします。矛盾した命令に質問したり、何もしないのではなく、相反した指示に従おうとしてしまうのです。
カタトニアの治療は,
①定型抗精神病薬を中止する(第一世代はもちろん第二世代(リスペリドンなど)もやめる。ただし第二世代は逆にカタトニアの治療効果があったとする報告もある)
②ベンゾジアゼピン系薬剤を投与する(症例報告をみるとlorazepam 0.5mg twice a dayなどからはじめ、lorazepam の高用量投与(最大で 16 mg/日)をする場合もあり)
③ベンゾジアゼピン系薬剤が無効な場合やあるいは悪性カタトニアと判断される場合には ECT の開始を検討する、
といった治療が現在の主流となっています。
統合失調症によるカタトニアではベンゾジアゼピン系薬剤の治療反応が乏しい傾向にあるといわれます。ですから非定型抗精神病薬(症例報告をみると、エビリファイ10mgから開始して一週間で20mgまでふやす。オランザピンを投与する。同時並行でロラゼパム3mg/dayを併用)やmemantine(商品名メマリー。NMDA受容体拮抗薬。一般に統合失調症の治療薬として考えられるのはNMDA 受容体作動薬です。NMDA受容体遮断薬による統合失調症様症状があるからです。)による薬物調整により良好な転帰を得た症例が報告されています。
しかし精神疾患としてのカタトニアの場合は、mECTを積極的に検討したほうがよいかもしれません。
参考文献
1 Successful Treatment of Catatonia: A Case Report and Review of Treatment Kevin Malone , Sall Saveen , Christopher M. Stevens , Shawn McNei 公開されているpdf
2 カタトニアに対するベンゾジアゼピン治療と電気けいれん療法 坂寄 健
3 カタトニアの「操作的診断・治療」化 上田 諭 公開されているpdf

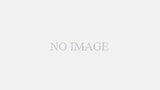
コメント