
日本でDVというと配偶者・パートナーからの身体、心理、性的暴力をいいます。これを目撃した場合、一般国民には警察や配偶者暴力相談支援センターへの通報の努力義務がありますが、被害者の意志を尊重したうえで判断しなければなりません。

そうですね。一方、児童虐待には身体、心理、性的虐待のほかにネグレクトがあります。DVの目撃も心理的虐待に含まれるため、例えば警察が激しい夫婦喧嘩に介入しそこに子供がいた場合、その子供は被虐待児とみなされます。

子供の安全確保を第一優先にするため、児童虐待を発見した場合児童相談所や福祉事務所への通報は義務となっており、ここがDVを発見したときの対処方法と違いますね。
「疑わしきは通報してあげよう」ということです。
もしも児童虐待の通報が誤りであっても刑事上民事上の責任を問われることは基本的にはありません。

家庭というのは、外界からの危険やストレスをクッションのようにやわらげ心身を回復させるために寄り添いあう「アタッチメント機能」があります。それが損なわれてしまうと自律性も損なわれますね。

そうですね。この問題は非常に難しいためネットの情報に頼らず、困っている方は警察、配偶者暴力相談支援センター、自動相談所虐待対応ダイヤル「189」に相談しましょう。
1歳くらいの子供が、養育者ではない大人に反応する様子から、安定型、回避型、アンビバレント抵抗型、無秩序無方向型、というアタッチメントパターンに分けられ、この順に不適応的となります。
児童虐待においてはそれ自体トラウマになりますし、健全なアタッチメントも失われます。(例えば大災害でトラウマをうけた場合、アタッチメントの対象である家族、友人は失われていないこともありますし、対象を失っても信頼できる人物やサービスにアクセスする能力は維持されている場合が多いでしょう。)ですから児童虐待におけるトラウマは、アタッチメントの障害も同時に起こすことが理解できます。そういう病態を統括して考えようとしたときの概念が、愛着トラウマというものです。
DSM-5をもとに愛着障害をわかりやすく図示すると以下のようになります。
アタッチメント障害(愛着に問題がある状態)
├── 反応性アタッチメント障害(RAD)
│ └── 閉じこもるタイプ、関係を避ける
│
└── 脱抑制型対人交流障害(DSED)
└── 開きすぎるタイプ、誰にでもなつく
愛着トラウマの治療は、トラウマ焦点化認知行動療法などがあります。薬物療法のストラテジーは確立されておりません。
心理・精神療法は「トラウマの統合」「愛着システムの安定化」が軸になっています。トラウマ体験の統合のために、アタッチメント、自己調整、能力という各積み木を下から積んでいくことが治療になってきます。

参考文献
1 ドメスティック・バイオレンスと児童虐待における精神科的介入 小平雅基: 精神科治療学 Volume 37, Issue 2, 133 – 138 (2022)
2 心的外傷や愛着の問題をかかえた子どもの治療と薬物療法の役割 著者: 小平雅基 出典: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 3, 285 – 293 (2022) 出版社: 星和書店
3 Trauma-Informed Intervention with Children: Integrating the CANS Assessment with the ARC Framework in a Clinical Setting – Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Attachment-Self-Regulation-Competency-ARC-Blaustein-Kinniburgh-2010-Kinniburgh_fig1_351589337 [accessed 29 Mar, 2024]
4 Blaustein M, Kinniburgh K. Treating traumatic stress in children and adolescents: How to foster resilience through attachment, self-regulation, and competency. New York: The Guilford Press; 2010.
5 Complex PTSD (特集 今の時代のトラウマ : 診断と評価)、臨床精神医学 54巻2号 2025年2月、千葉 比呂美ほか
*ご利用上の注意について
本サイトは、患者様、医療関係者の皆様などに日常生活や仕事が少しでも快適になることを目的としております。 また、本サイトに掲載されている情報は管理、点検しておりますが、必ずしも常にその確実性が保証されるものではなく、情報のご利用については、ご利用される皆様の判断にまかせられることを前提としています。 本サイト運営においては適時情報の更新等行って参りますが、万一本サイト情報の利用の結果、不都合や不利益が発生することがありましても、情報の提供者側は最終的な責任を負いかねますことをご理解いただき、慎重にご利用くださいますようお願い申し上げます。
本サイトにリンクを希望される場合は、あらかじめ下記の注意事項すべてに従ってください。 また、本サイトへのリンクにより、万一、貴社または貴殿が損害を被った場合、および第三者との間に何らかの紛議が生じた場合でも、損害賠償等の義務・責任を負いませんので予めご了承願います。 本サイトへのリンクは、ホームページを利用されるユーザーの皆様の便宜を図ることを目的とする場合に限ります。それ以外本サイトの目的に該当しない下記の場合におけるリンクは固くお断りいたします。
1. 本サイトにリンクすることにより、本サイトと特別な関係があるように見せかけたり、リンクの設定自体を営利目的とするもの。
2. 本サイトの社会的信用を損ない、または当院に経済的損失が生ずるおそれがあるもの。
3. 違法のおそれ、または公序良俗に違反するおそれのあるサイトからのリンク。
4. フレーム・インラインフレーム等の技法により本サイトのコンテンツであることが不明確となるもの。
本サイト上のコンテンツ(情報、資料、画像等)の著作権については、本サイトが保有または管理しております。本サイトの許可なくコピー、販売・転売、転用など2次的に利用することは固く禁じます。 本サイトの許可なく上記著作権に関する一切の再利用は法律で禁じられています。

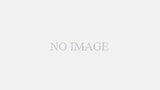
コメント