
双極性障害のうつ病相について治療ガイドラインでは気分安定薬や非定型抗精神病薬が推奨されています。うつ病相の上位の治療チョイスはリチウムやクエチアピンであり、ついでオランザピンやラモトリギンが推奨されています。抗うつ薬の使用については単独/併用にかかわらず、推奨にはなっていません。ただし双極Ⅱ型のうつ病相には新規抗うつ薬について推奨されるまでには至っていませんが、認容されつつあります。

双極性障害のうつ病相で低用量(25~75㎎)スルピリドが有効との報告もあります。

双極Ⅰ型とⅡ型にわけて詳しく考えてみましょう。
双極Ⅰ型うつ病にはリチウムや非定型抗精神病薬のクエチアピン、オランザピン、ルラシドン([ドン」から想像つくようにSDA])が推奨されています。それでは双極Ⅱ型うつ病のファーストチョイスはなんでしょうか。

・双極Ⅱ型障害は遺伝的に単極性うつ病に近い、
・双極Ⅱ型うつ病にリチウム(双極性障害の予防効果はあり)やクエチアピンは無効、
・双極Ⅱ型うつ病にSSRIやSNRIは効果があり、急速交代型にも有効性や予防効果がある、
・双極Ⅱ型うつ病に抗うつ薬を使用しても躁転率は低い、
などの報告があるのです。

双極Ⅱ型うつ病の薬物治療は、「双極」という名前にとらわれて双極Ⅰ型うつ病のそれに準ずると考えるよりも、単極性うつ病に準じた方が良いのかもしれませんね。

双極Ⅰ型なのか双極Ⅱ型なのかをしっかり鑑別する必要があるます。
双極Ⅰ型はⅡ型と比較して、
・社会的職業的機能に著しい障害のある躁、
・性差がない(Ⅱ型は女性に多い)
・発症年齢が低い、
・内分泌代謝疾患や肥満が多い、
・自殺リスクが低い、
などの特徴があります。

双極性障害のうつ病相について実際の臨床では、気分安定薬や非定型抗精神病薬を使ってもうつ症状がわるいときにごく少量の新規抗うつ薬を上乗せすことがあります。それでもまだうつ症状が治療困難である場合は抗うつ作用をあげなくてはならず、推奨はされませんが気分安定薬を中止して抗うつ薬単剤にせざるを得ないこともあるかもしれません。

お薬の使い方はとても難しいので、お困りの方はネットの情報に頼らずに必ず病院に行きましょう。
遺伝学的差異(≒生物学的差異)を調べると、双極性障害は単極うつ病より統合失調症に近縁であることがわかっています。事実DSM4では双極性障害、単極うつ病を「気分障害」としてまとめていましたが、DSM5からは両疾患を分けて分類しています。臨床症状をみると双極性障害は統合失調症よりもうつ病との区別が難しいので、遺伝学的分類と、本人や臨床家の印象は隔たりがありますね。
気分安定薬の濃度ですが、リチウムもバルプロ酸も、病相期には高めの濃度を目指し、維持期は少し下げてもよいといわれています。リチウムでいえば、病相期は0.8-1.3、維持期は0.6-1.2です。バルプロ酸は、病相期は50-100、維持期は45-100位です。
双極性障害の治療で一番難しいのが、うつ病相の治療ではないでしょうか。
たいていの場合は、ラモトリギン単剤、ラツーダ単剤、リチウム単剤、ラモトリギン+ラツーダ、リチウム+ラツーダ、などでうつ病相の多くは改善されます。それでも改善されない場合はどうすればよいでしょうか。
双極性障害のうち、Ⅰ型ではなくⅡ型で、躁鬱混合状態ではなく、躁転や賦活症候群もない場合、SSRIやSNRIを使う治療者もいるようです(5)。抗うつ薬の躁転率は、SSRI、SNRI、三環系の順に高くなるといわれ、ノルアドレナリンが躁転に関わっていると予想されています。SSRIやSNRIを使う場合は気分安定薬や非定型抗精神病薬と併用すると、抗うつ作用が抑制される可能性があり、場合によってはSSRIやSNRIの単剤使用も検討してもよいかもしれません。
さらに双極性障害のうつ病相の治療としてプラミペキソールやロピニロールなどのドパミン受容体アゴニストによる抗うつ効果の報告があります。スルピリドはドパミン受容体アンタゴニストでありますが、少量(300㎎以下)の場合は前シナプスのD2受容体遮断によりシナプス間隙においてドパミンが増える、つまりドパミン作動作用をもつといわれています。ゆえに低用量スルピリドが双極性障害のうつ病相に効果があるのかもしれません。プロラクチン血症(月経異常や乳汁分泌)は高頻度にある副作用のため、閉経前の女性にスルピリドは使わない方がよいでしょう。その他にもパーキンソン症候群、遅発性ジスキネジアといった副作用にも注意すべきです。
参考文献
1 双極Ⅱ型うつ病の薬物治療 森下 茂: 最新精神医学 Volume 27, Issue 1, 75 – 79 (2022)
2 双極Ⅱ型障害の薬物療法ガイドラインについて―抗うつ薬の位置づけと近年の知見を含めて― 塩田 勝利 公開されているpdf
3 双極性障害のうつ状態に対する低用量スルピリドの有効性と安全性 奈良県立医科大学 井川 大輔 臨床精神医学第52巻第2号 – アークメディア
4 双極性障害における気分安定薬と抗精神病薬の用量 著者: 岸 太郎, 佐久間健二, 波多野正和, 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 12, 1319 – 1322 (2022)
5 双極性障害:抑うつエピソードに焦点をあてて、著者: 寺尾 岳、出典: 臨床精神薬理 Volume 25, Issue 6, 633 – 638 (2022)
6 気分障害におけるエピゲノム研究、菅原裕子 他, 臨床精神医学 51 (10) 1107-1111, 2022.
*ご利用上の注意について
本サイトは、患者様、医療関係者の皆様などに日常生活や仕事が少しでも快適になることを目的としております。 また、本サイトに掲載されている情報は管理、点検しておりますが、必ずしも常にその確実性が保証されるものではなく、情報のご利用については、ご利用される皆様の判断にまかせられることを前提としています。 本サイト運営においては適時情報の更新等行って参りますが、万一本サイト情報の利用の結果、不都合や不利益が発生することがありましても、情報の提供者側は最終的な責任を負いかねますことをご理解いただき、慎重にご利用くださいますようお願い申し上げます。
本サイトにリンクを希望される場合は、あらかじめ下記の注意事項すべてに従ってください。 また、本サイトへのリンクにより、万一、貴社または貴殿が損害を被った場合、および第三者との間に何らかの紛議が生じた場合でも、損害賠償等の義務・責任を負いませんので予めご了承願います。 本サイトへのリンクは、ホームページを利用されるユーザーの皆様の便宜を図ることを目的とする場合に限ります。それ以外本サイトの目的に該当しない下記の場合におけるリンクは固くお断りいたします。
1. 本サイトにリンクすることにより、本サイトと特別な関係があるように見せかけたり、リンクの設定自体を営利目的とするもの。
2. 本サイトの社会的信用を損なうおそれがあるもの。
3. 違法のおそれ、または公序良俗に違反するおそれのあるサイトからのリンク。
4. フレーム・インラインフレーム等の技法により本サイトのコンテンツであることが不明確となるもの。
本サイト上のコンテンツ(情報、資料、画像等)の著作権については、本サイトが保有または管理しております。本サイトの許可なくコピー、販売・転売、転用など2次的に利用することは固く禁じます。 本サイトの許可なく上記著作権に関する一切の再利用は法律で禁じられています。

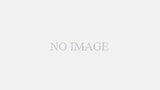
コメント